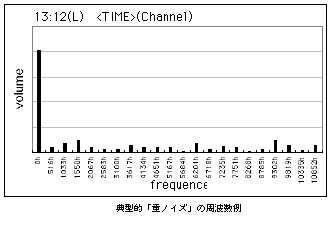第67回例会報告
[戻る]
日時:2001年3月20日(土) 13:00 〜 17:00
会場:名古屋市中区栄 愛知芸術文化センター 12F アートスペースE・F
【卒論修論発表会】
18世紀末のホルン書法の変遷 −−協奏曲を中心に−−
愛知県立芸術大学 小原道雄
今回の研究では古典派の中で起こったホルン書法の変化を、協奏曲を中心にホルン書法の観点で考察した。その際に過去の研究とは異なった切り口から出発するために、C.シュターミツのホルン協奏曲と、A.ロゼッティ、G.プントによるその書き換えの問題を題材として取り上げ、その書き換えの背景に見られるホルン書法の変遷を明らかにする、という形で次第に取り上げる範囲を広げた。また、協奏曲以外のジャンルとの関連についての所では、過去にもあまり触れられてこなかった交響曲のTutti部分でのホルン書法にも触れた。
まず最初にシュターミツのホルン協奏曲とロゼッティ/プントによって書き換えられた作品を比較すると、シュターミツの作品において高音域をゆったりと歌うバロック期以来のクラリーノ的な要素を持った部分が、ロゼッティ/プントによって全て中・低音域に収まるように書き換えられていた。これにより高音域のコントロールから複雑なハンドストップ操作へと、ヴィルトゥオーソ性が変遷したことが認められた。この3人より以前に書かれたF.J.ハイドンの協奏曲に対してはストップ操作の要求度が上がっており、3人より後のウェーバーの作品ではさらに複雑で正確なストップ操作が要求されていた。同時代のモーツアルトと比較すると、ロゼッティのストップ操作がより高度であった。これにより、ロゼッティが古典派のホルン協奏曲ではその書法の変遷の境目になっていると考えられた。
交響曲でのホルン書法については、ロゼッティ以前のJ.シュターミツの交響曲ではクラリーノ的書法によってホルンに旋律が与えられており、ロゼッティ以降のベートーヴェンやメンデルスゾーンの作品では旋律のみならず、和声の補助、ユニゾンの時にもストップ操作を伴っていた。これに対してロゼッティと同時代になる彼自身の、或いはモーツアルトの交響曲では中音域の自然倍音による和声の補助が殆どであった。
以上のことから、ホルン史においてハンドストップ奏法が定着するのは、ジャンルによって差があることが分かった。ロゼッティが協奏曲でストップ奏を開拓していた時期は、交響曲のホルンパートにとっては停滞の時期であったと考え、さらにこれらのことから古典派のホルン書法が変化しつつあった時期を、協奏曲、交響曲両方のジャンルから指し示すことができた。
ここでもう一度シュターミツとロゼッティ/プントによる書き換えの問題に立ち戻ると、これは古典派のホルン音楽における大きな変動を表すアスペクトとして捉えられることが分かった。
療法における「強化子」としての音楽の機能について
-エヴァン・ルードの療法理解を高齢者対象音楽療法セッションに投影して考察する-
名古屋音楽大学 出口 あゆみ
音楽療法の領域において、音楽が療法と結びつくことによって顕わになる機能について検討することは、その本質に迫る上で重要である。そして、その為には理論的な側面からのみ検証するのではなく、現実の療法の場においても音楽がどのような効果をもたらすか、何故音楽が強化子となり得るのかを観察することが必要不可欠になってくる。
そこで、本論文は音楽と療法の問題を様々な視点から問い続けているエヴァン・ルードの理論と、筆者が関わっている高齢者対象の音楽療法セッションでの音楽の応用との二つの面から、療法における音楽の機能について考察した。
まず、エヴァン・ルードはこれまでの音楽療法の研究は治療的側面のみが強調され、音楽そのものの療法的な意義の追求がおろそかになっていることを指摘する。その結果、音楽療法に対する見解が一面的になり、音楽の機能も表面的にしか理解されないといった弊害が生まれてくる。それを克服するために多面的に眺め、文化的なカテゴリーの一環として捉えることの必要性を強調し、そのうえで音楽が何故療法上の「強化子」となり得るのかを追求する必要があることを主張している。
そして、筆者が関わっている高齢者対象の音楽療法セッションより音楽が「強化子」として作用する領域は、記憶の想起・コミュニケーションの回復・身体機能の維持が主になっているという考えが導かれた。更に、その三つの関係を考えたことによって、コミュニケーションの回復は記憶の想起・身体機能の維持の二つに働きかけることが可能であり、その機能が「強化子」として作用することを理解できた。また療法における音楽の機能について考える際には、音楽のみを問題にするのではなく、療法に関わる様々なことが互いに影響を及ぼしていることを認識するとともに、広い視野から捉えようとすることが重要であることを改めて感じた。
このように、エヴァン・ルードの理論と実践経験をすり合わせることによって、「強化子」としての音楽の機能について可能な限り追求することができた。しかし、音楽療法の現状においては、理論と実践の融合性を求める研究はあまりなされていない。そして、音楽療法を多面的に捉えることを今後の課題とすべきだと考えているエヴァン・ルードの理論は今後の音楽療法の為の導き手として高い意味をもっていることも理解することができた。
ノイズ音楽におけるテクスチャ分析 〜Merzbowの作品を中心に〜
名古屋市立大学芸術工学部 廣瀬麻弥
現在、日本には「ノイズ・ミュージック」という音楽のジャンルが確立されている。その第一次世代ともいうべき秋田昌美の"Merzbow"が奏でるその音楽は過去における音楽作品の形態からかけ離れた音を発している。本論は「ノイズ・ミュージック」がどのような音楽なのかをMerzbowの作品を分析することによって証明する。
第2章歴史背景ではノイズ音楽の発想の基盤となる過去における作曲家、芸術家等を取り上げノイズ音楽の背景を垣間見ることを試みている。概念や思想部分ではイタリアの未来派ルイジ・ルッソロ(Luigi Russolo)から始まり、1970年以降ヨーロッパにおいて興るインダストリアル・ミュージックのムーブメントが強く影響を及ぼしていると考察される。またカットアップ・メソッドはアメリカのウィリアム・バロウズ(William S. Burroughs)らによるビートニクスにおいて考案されたものを音楽の手法に用いている。
分析にはいる前に準備研究として分析方法で用いるフーリエ変換の研究、人間の耳の構造において内耳の基底膜がどのように周波数を知覚しているかを第3章では研究している。
Merzbow自身の研究として過去の作品と取り上げ分析したものが第3章変遷であり、文献と帯域別グラフを作成することによって曲の相違を述べている。前半期の1979年から89年までは日常のものから音を奏で録音した作品や、ロックのようにメロディーやリズムがあるものが多く残されているが、89年のヨーロッパツアー以降の後半期に入るとNoiseElectronicsという装置の登場により作風の劇的な変化がみられる。
そしてNoiseElectronics現在のMerzbowが積極的に行っている特色ある曲を分析したものが第4章特色曲の分析研究である。曲全体の周波数を超低音域0〜86Hz、低音域〜1033Hz、中音域〜4048Hz、高音域〜10938Hzにわけている。さらに変化の少ない一部分を切り取りその周波数分布をグラフにした。既存の楽器音では得られない周波数分布を見せていることがそこで明らかにされた。その内容は低音域、特に80Hz以下の超低音が全体で相対的に高い出力値を示しているものである。高い出力値の超低周波とその他の音域の音波を含むその音色は特筆すべき倍音構造を持たないので重く濁った印象を与えているということが証明された。
第5章まとめでは本論の研究・分析結果の結論としてMerzbowのノイズ音楽とは「重く」「濁った」「不確定」な音楽であることを述べ、さらにその音楽的社会性を簡単にまとめている。
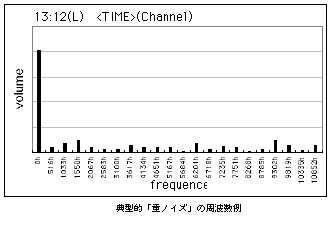
ある発達障害児の音楽療法時における行動の変容について
-『促進』及び『受容』・『拒否』の観点からの分析を通して-
愛知教育大学大学院 奥村千春
研究目的: 1年間、愛知教育大学内で行った音楽療法におけるある発達障害児K児の行動の変容について、促進、受容、拒否の観点から明らかにする。 セッションは、K児の認知活動を活発化させること、積極的なコミュニケーション行動を促すことを主要課題とした。そこで、本論では、初期段階のアセスメントセッションとその結果を踏まえた改良後のセッションを比較することを通して、K児の行動にどのような変容がみられたかをとくに、認知行動とコミュニケーション行動に着目し、考察する。
対象児: K児は現在、小学3年生であり、母親同伴のもと普通学級に通う。障害は、重度の知的障害及び左半身の麻痺であり、言語の遅れが2歳の頃から指摘されていた。
分析方法: セッション分析は幼児の行動観察に用いられる時系列分析の方法に改良を加えたもので、セッションをビデオ録画し、時間に伴う行動の連鎖を行動カテゴリーに分類し、行動を発現させる条件や行動発達のパターンを明らかにするという手法を用いた。
結果と考察: アセスメントセッションからK児はセッション全体を友好的に受け入れているものの、認知課題では積極的な受容態度がみられないこと、また、セラピストによる言語的な促進より音楽的な促進に対して、積極的に受容する確率が高いことがわかった。その結果、音楽的な促進を意識的に用いてセッションを進めること、K児に合った認知課題を設定することがK児の音楽療法による発達を促すポイントであると判断した。
改良した最終的な7回のセッションでは、K児自身の促進や積極的拒否が現れ、自己主張が現れた。認知活動では、言葉対絵対応から物対物対応への課題の転換により、K児に課題意識が芽生え、一貫性や再現性のある行動が現れた。また、音楽を用いることにより、認知課題に音楽遊びとして要素が加わり、認知活動が活発化していく可能性が認められた。
コミュニケーション活動においては、大太鼓(セラピスト)とトライアングル(K児)でのやりとりが進行していくうちに、K児が自発的に即興演奏を行うなど、アセスメント時にはみられなかった自らの促進行動が認められるようになった。つまり、音楽的なコミュニケーションの促進によって、言語による表現能力に欠ける子ども達であっても、彼らの創造的な自己表現を引き出すことが可能であることが確認された。
[戻る]